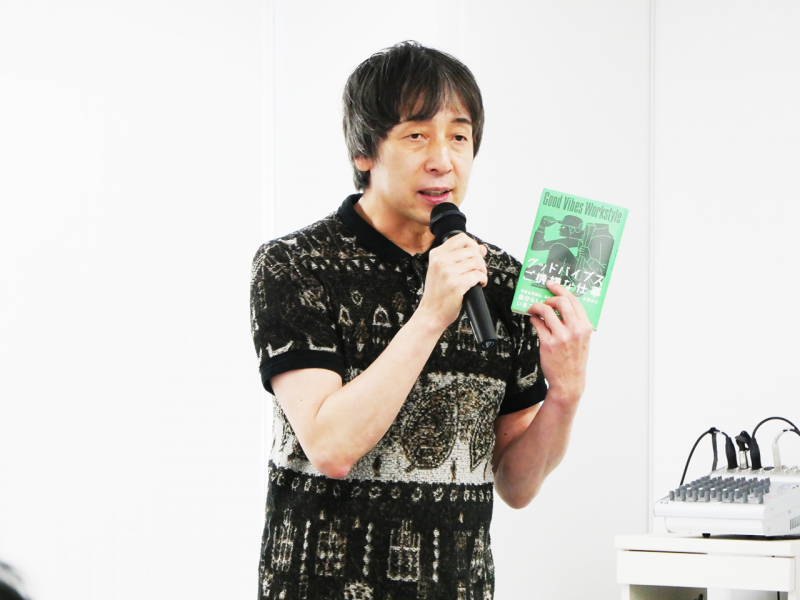DPC RECRUIT
フォローアップ研修
Vol.03〜第三回DPC研修〜
〜あたたかい言葉、そばにいる言葉、そぎ落とされた言葉〜 伝わらない、から始まるコミュニケーション

Vol.03 研修開催日:2017年11月5日
極地建築家
村上 祐資(むらかみ ゆうすけ)
1978 年生まれ。極地建築家。 “はじまりの家” としての宇宙の家。“人間の根をおろす力” からうまれる、美しい暮らし方や住まい。地球上の「極地」とよばれる境い目に身を置き、それらを問う。 現在、米The Mars Society が実施する、“地球にある火星” で行う、長期シミュレーション実験「Mars160(2016-17)」の唯一の日本人クルー(副司令官)として、模擬火星探査ミッションに従事中。 第50 次日本南極地域観測隊越冬隊員(2008-10、地球物理観測担当)、JAXA 閉鎖BOX(2004)、エベレストB.C.(2010)、 シシャパンマB.C.(2011)、富士山測候所(2010-12)、MDRS Crew144(2014)、NASA「HI-SEAS」ファイナリスト(2015)。 NPO 法人日本火星協会、理事およびフィールドマネージャー。防災士。JFN ラジオ番組「ON THE PLANET」水曜パーソナリティ。慶應義塾大学大学院AUD プログラム修士課程修了。東京大学大学院工学系研究科博士課程退学。
Program
参加型のワークショップ
直線距離で1万4千キロ離れた日本と南極。最大40 分の通信ディレイが発生する地球と火星。そして帰還するまでに何年もかかるミッション。まるで浦島太郎のように、相手とのコミュニケーションの手がかりを失ってしまう経験。僕はそんな極地で暮らしてきました。距離と時間の隔たりは、僕らから「あたりまえ」を奪うのです。
今回の講義では、みなさんからあたりまえを奪います。そこからコミュニケーションをはじめてみたいと思います。
第3回目のDPC スペシャル社員研修企画を終えて

『伝わらない』からはじまるコミュニケーションをテーマに今回極地建築家の村上さんを講師に研修会を行いました。
村上さんは『私がやっていることは冒険家でも探検家でもない、踏査(とうさ)である。』と・・・。極地に行きそこで普段と変わらぬ生活を送る、冒険家や探検家のようにすぐ先にゴールは見えない。そこでの様々な価値観を持った人達とコミュニケーションをとっていく作業は、場所は違えど日々薬局で働く私達と近いのではないかと思います。
講義では相手の様子を窺うように話しかける言葉= 発見言語、相手にyes、no を求めて発する言葉= 説明言語、を使い分けコミュニケーションを円滑にはかるという話があった。
具体的には、説明言語を多用することで相手を傷つけたり、気持ちを揺らがせたりしてしまい争いのもととなるため、意識して発見することばを使うようにするというものだ。
ワークショップでは『伝わらない』ということを理解するために、手旗信号を使って説明言語である基本信号の原画(数字、はじめます・わかりました・間違えました・どうぞなど)と各チームで自由に1つだけ使える信号を使って数字の組み合わせを正確に伝えるゲームを行った。
私のグループでは『OK=大丈夫だよ、あってるよ』と様々な捉え方の出来る発見言語を作り、それが要所々々でチームの助けとなり、とても重要なことばになった。
このワークショップではスムーズな流れでやることよりも途中でエラーが生じた際に対応を一つ一つ確かめ合うことの重要性を学んだ。最後に、村上さんが『その人の無関心に注目する、それこそがその人の人となりを表しており、その人のミスに繋がってくる。ミスを事前に察することでチームとしてのミスをなくすのだ』と言っていました。いくら選ばれたプロでも厳しい環境においてはミスをするし、習慣を殺されることで苦しみ、満たされないことで欲望を抑えられなくなり、我を忘れて他人を傷つけてしまうことがある。そのことでチームが壊れてしまうのである。
『鯨瞰(げいかん)= 俯瞰(鳥瞰)ではなく、鯨のように下からチームを見渡すこと』で全体を冷静に把握する村上さんの視点は常に意識して私も出来るようになりたい。(報告者:吉村 司)
「僕は冒険者ではない」(文章:本田 英郎)

村上祐資先生をお迎えしての研修を終えてーー不確かなコミュニケーションという希望「いま、火星にもっとも近い男」ーー人は村上祐資さんをそう呼ぶことがある。
しかし私から見れば、「火星にもっとも近く、かつ、もっとも遠い男」なのが村上さんである。建築を専門にしながら、かつて日本の南極観測隊員として極地に暮らし、その後も火星探査の実験プロジェクトで北極やアメリカの砂漠で暮らした村上さん。その村上さんの未来への視線は、地球上の極地をはるかに超えて、人類が到達可能な宇宙空間の極地に向けられているようだ。しかし村上さんは、自分は冒険家(者)ではないと言う。彼の関心は冒険として極地を制覇・踏破することではなく、辿り着いた先での人の暮らしや人々のコミュニケーションそのものに向かうのである。
極地で人が集団で暮らすとき、もちろんそこに人と人との対話=コミュニケーションが生まれる。それは私たちの日常生活と同じだが、極地ゆえ、一定期間ある限定的な閉じられた空間のなかで人間関係を営まなければならない。さまざまな資質、価値観、専門、背負っているものが異なるなかで、いかにしてその集団の意思疎通を維持してゆけるのか。これもまた、私たちの仕事や生活に近いとも言える。ただし、南極では「外」の居酒屋に気軽に散歩に出かけて気晴らしはできない。外は凍てつく寒さであり、命がかかっているからだ。
以前、村上さんはある研究会でこう語っておられた。
自らすすんで冒険へと向かう人々は、たとえどんなに過酷な環境のなかにあっても〈往復切符〉を持った人たちではないのか。自然災害で被災した人々のように、先の見えない〈片道切符〉しか持ち得ない人たちと、どうやって結びつけて考えたらよいのか──。
僕はその問いに対し、今以て確かな答えを持ってはいない。冒険は〈片道切符〉であってはいけない。それが冒険者たちにかせられる、おそらく唯一といっていい使命である。
しかし僕は冒険者ではない。あえて例えるなら、自らを実験台にして大西洋を漂流したボンバールのような実験者であろうか。
そして実験もまた〈片道切符〉であってはならない。
しかるに実験者は、実験を以て真実を語ることの危険性を常に認識しておく必要がある。
その認識を持つ実験者だけに許される〈片道切符〉の旅。
それがつまりは思考という名の漂流なのだ。
思考という名の〈片道切符〉の旅。
そこから日常の〈生きる〉を考え直すこと。僕らの未来のために、生きるための知恵を探そう。
私たちの日常の仕事におけるコミュニケーションは、〈片道切符〉なのだろうか〈往復切符〉なのだろうか。お客様に対する丁寧な言葉や態度は、対価以上の見返りを求めない〈片道切符〉のようでもあるし、村上さんの言葉からは少し飛躍するが、そこ交わされるお客様との会話や笑顔、お礼の言葉などによって〈往復切符〉のコミュニケーションとなることもある。
しかし、コミュニケーションはつねに不確かである。不安定である。相手になかなか自分の感情や意図が伝わらないからといって、自分を責めすぎても相手を責めすぎてもうまくいかない。そこにはつねにコミュニケーションの漂流実験が伴う。相手にどう伝わるかは自分では完全にコントロールできない、ひょっとしたらあまり伝わらないかもしれない、という意味で、コミュニケーションはつねに漂流するリスクを負った実験であるとも言えるだろう。
伝える手段を奪われたコミュニケーションの実験

今回の研修では、言葉、身振り手振り、表情、これらをすべて使用できない状態で、手旗を使った「伝える/伝わる」「伝えられない/伝わってこない」というユニークな実験を行なった。
手旗は、船舶どうしのやりとりを想像するとわかるが、正確性と信頼性がすべてである。言葉は使えない。遭難した状態を思い浮かべればわかるように命がかかっている。その意味で手旗は正確な言語であることが必須である。しかし時に、人間の会話のように言い間違いも生じる。その時にそれが命取りにならないように、情報を訂正し正確な情報を送り直させねばならないことも生じるだろう。
本研修では、手旗で信号を送る人、それをいったん中継する人、中継者から最終的に信号を受け取る人、の3人に別れ、最初と最後の人にはそれを観察しアシストする役割の人がそれぞれ1名ずつ与えられた(合計5人のチーム)。詳細は省くが、写真から想像をしていただきたい。これがじつに面白いのである。
村上さんが「157302749320」などとランダムな数値を決め、その数値を手旗信号で相手に正確に伝えようとするというコミュニケーションの実験なのだが、それぞれの数とそれを表わす手旗のカタチ(型)を忘れたり、焦って間違えたり、いろいろな齟齬が生じて、参加者は思い通りにいかず、苦笑する。それぞれの個性も出てきて、見ていてつい笑ってしまう。
結果として、限定的な制約条件のなかで正確に伝えることがいかに困難かを体感することになった。村上さんの与えた「正確な数値」に近づいても、なかなか完璧な正解には至らないのだ。
ところが、である。試行錯誤を繰り返し、なかなかうまく「伝えられない/伝わらない」ジレンマのなか、研修の後半のほうで、ひとつの旗のカタチをコミュニケーションの補助として自由に使っていい、という新ルールが特別に与えられる。そして、それを話し合うためのグループごとのミーティングを数分間行なう。
これがたいへん興味深いものとなった。自分たちで考えた便利な手旗信号のツールがひとつ増えるだけで、互いの意思の疎通がまったく変わってきたのだ。そのうえで行なった最後の手旗は、3つのグループが全員正解となったのである。みんな、無事、遭難を免れたわけである。
しかし興味深いのはこの先だ。一見すると、与えられた信号=型しか使えなかったミーティング前の状態は、みんなが不慣れ/未成熟/未完成/ぎくしゃくのコミュニケーションに見えていた。それに対して、ミーティングの後は、意思の疎通が慣れてきて/成熟し/スムースに流れたように見えた。
確かにそういう側面はあるけれど、しかし、組織における人間同士のコミュニケーションを考えてみると、むしろミーティングの後のスムースさというのは、何度も繰り返しているうちに「慣れ」、それがかえって良くない「惰性」に陥ってしまう可能性も逆にあることを考えさせる。また、他のアイディアを考えずにずっとそのアイディアに固執しがちになること、などのマイナス面も出てくるかもしれないのだ。
逆に、ミーティングの前のほうが、むしろ、不慣れ/未知/未完成/伝わらない不安感があるからこそ、みんなが手探りで伝えようと懸命になった、というプラスの見方もできる。多少の不正確はあったにせよ、使ってはいけないはずの表情や身振り手振りもつい出てしまったりして、むしろみずみずしいコミュニケーションが成り立っていたと見ることもできるのである。
こうしたコミュニケーションの両面性については、これから先も考え続けるためにも、私の受け取った最終的な印象としてみなさんと共有しておきたいと思います。日常生活や仕事におけるコミュニケーションは、不正確で不確かだからこそ、なかなか慣れず、完成せず、でもだからこそ自分の言葉や態度、伝える際のクセを検証し、終わりなきコミュニケーションの漂流実験はみずみずしく続いてゆく……そんな希望が脳裏をよぎりました。
補遺̶̶通常、中継を入れた3 人での手旗は、本来の通信では行ないません。今回のワークショップにおける手旗信号のやり方は、通常のものに独自のアレンジを加えています。